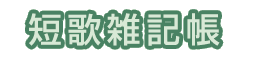
| 「いざ生きめやも」など 先日ある会合で宮英子さんにお会いした時に、堀辰雄の小説『風立ちぬ』に出て来るヴァレリーの詩の一節の訳語の「風立ちぬ、いざ生きめやも」について松尾聰氏が論じていることを教えていただいた。それは、私が以前「いざ生きめやも」は語法上は「いざ生きざらめやも」とすべきところだと書いたのを記憶されてのことであった。松尾氏は「いざ生かざらめやも」と言うべきだと主張されているということで、さっそく宮さんからその文章のコピーを送っていただいた。 それは、由良琢郎氏発行の「礫」の本年十月号に「ことばの休憩室」(49)として、松尾氏の書いた「風立ちぬ、いざ生きめやも」と題する一文である。要点を紹介すると、 その「いざ生きめやも」は、「さあ、(心をふるいおこして)生きないでいられようか。断乎として生きぬこうぞ」の意として読者に受け取られるべく作者は考えていたにちがいないと 思うのであるが、「めやも」は・・・・・・専ら反語であって、例外はない。従って「生きめやも」は「生きるだろうか、いや生きることはないだろう」の意でしかない。それを作者の堀さんは知らなかったのだろうか。そんなはずはない。 として、東大国文科の卒業生で「かげろふの日記」も書いた堀辰雄が上代中古に行なわれた「めやも」の語意を知らなかったとは到底考えられない、「誤訳」であっても一般の知識人は「いざ生きめやも」を「さあ、生きないでいられようか、生きてやるぞ」の意に、何の抵抗もなく理解するにちがいないと判断したのだろうと思いやり、更に「いざ」という語気にあおられて「生きないでいられるものか」の意味にならないわけにはいかないようである、と松尾氏は「自分なりに納得」されるので、その思考過程がおもしろく、堀辰雄の「誤用」に同情的である点に私も感じ入った。しかし何と言っても無理が通れば道理が引っ込むの印象は否み難く、赤彦の言う「語法の超越」として認めるのもためらわれる。本人もはたして「誤用」と承知のうえであえてこの詩句を使ったものであろうか。それこそ「いざ」に助けられて作者も疑うことがなかったのではあるまいか。 なお自動詞「生く」は、中世からは上二段活用に転ずるが、上代、中古を通じては四段活用動詞だったから、「生く」に「ず」を添えれば「生きず」ではなく「生かず」である。「生きざらめやも」とはならないのである。 と説明される。(宮英子さんはその点を注意されたのであった。)この点に一言したい。 あたたかく飯くふことをたのしみて今しばらくは生きざらめやも 『たかはら』 がある。「生き」と上二段活用を使用している。松尾氏は「『めやも』は万葉集には、かなり用例があるが、中古ではすでにほとんど用いられなくなったほどの『古語』で」と説くが、その「めやも」を使うにしても「生きざらめやも」として別にちぐはぐでなく自然に受け入れられるのである。 大君の勅をかしこみちちわくに心はわくとも人にいはめやも の中世初めの『金槐集』の実朝の歌である。万葉集人麿の「昔の人にまたも会はめやも」などから学んでいるには違いないが。 春の火に燃えたるあとを登りをり黒々として生けるもの見ず 斎藤茂吉『たかはら』 思いつくままに三首を引く。「生ける」は、「生け」に完了の助動詞「る」がついたので「生きている」という意であり、動詞の連体形の「生くる」とはやや意味あいが違うのである。以上は松尾氏の文章に触発されたので、反論ではない。 |
|
| ← → |