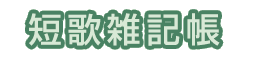
|
「我はさびしゑ」 万葉時代には普通に用いられていた言葉がその後、プツッと糸が切れたように使われなくなったのに、近代になって歌言葉として復活したものは少なくない。例えば万葉の「田子の浦ゆ打ち出でて見れば」が、新古今では「田子の浦に・・」と訂正されて「ゆ」は忌避されたのに現代では多くの歌人がはばからずにこの「ゆ」を作歌のなかに持ち込んでいる。万葉の「家聞かな、名告らさね」などの終助詞の「な」「ね」なども平安時代以後は殆ど用例がないが、近代現代の作品では、さほど珍しくない。その具体例は今は略するとして、同じく古い終助詞の一つに「ゑ」というのがある。万葉では「よしゑやし」という慣用句に使われたほかには「心はよしゑ君がまにまに」などの例もあるが、それ以外には次の二例のみ。山の端(は)にあぢ群騒ぎ行くなれど我は寂(さぶ)しゑ君にしあらねば (四八六) 実は、私は法務省が月に一度出す「人」という新聞で全国の刑務所に服役する人の出詠する短歌の選を任されている。最近東北方面の人の出詠歌に「我は寂しえ」という結句を持つ歌があった。(メモを紛失して全部引用できない。)この場合は新仮名の「え」であったが、現代ではこの終助詞は、このように一般化しているのである。万葉にも少ないこの「ゑ」を復活させたのは恐らく明治の根岸派の歌人であろう。 からまるを否とたれかいふつゆ草の蔓(つる)だに絡め我はさびしゑ 長塚節の明治四十四年の「病中雑詠」のなかに見える。「さびしも」などと言わずに「さびしゑ」と言ったところが効果をあげている。これ以前にも用例はあるかも知れない。そのほかの近代歌人の歌を少し引いてみる。しとしとと身にふりきたる夕暮れの今は淋しゑ立ちても行かな 中村憲吉『馬鈴薯の花』 あと五年婚姻不可を伝へくる蜚語と云へども吾は悲しゑ 以下は蛇足であるが、私が少年時代を過した信州諏訪地方では、女性の言葉として東京の娘ならば、ヤッテモイイワというところをヤッテモイイエと言う。そのほかワルイエ、チガウエ、モウ行クエというように話していた。この言い方は、今でも残っているようだ。私は当時ひそかに万葉の「我は寂しゑ」の「ゑ」と関係づけて考えていたのだが、それはどういうものか。 江戸時代の若い女性の言葉にはチガウゾエなどという言い方があったようだから、直接的にはそういう言葉と結びつけて考えるべきかも知れない。しかし万葉時代にもすでに衰えかけていた「寂しゑ」式の「ゑ」の流れが、地下水脈のようにほそぼそと後世にも伝わり、近代になって短歌に復活したと考えていいならば、何か心が楽しくなるのである。
|
|
| ← → |