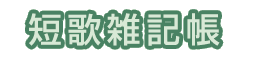
|
「雪ふる音」について 草野より暁霧の立つなべにわが眼は覚むる病む現実に 津田治子さんの遺歌集「雪ふる音」を、今回しみじみと読み、まずこういう歌に心打たれた。今まで雑誌ではぼんやり眺めていたにすぎなかったが、一冊の歌集にまとめられたのを読むと、作者の人生や人間や情念が色濃く浮かびあがって来て、改めてこの人を認識したというわけである。この歌集の前に「津田治子歌集」というのがある由、私はまだ見ていない。しかし津田治子の歌及び人を知るにはこの「雪ふる音」一冊で十分なのではあるまいか。そういう充実感がこの歌集にはあるように思われる。 津田さんは巻末の年譜によると、明治四十五年佐賀県の生まれ、十八歳で発病している。数日前にテレビでハンセン氏病に関する座談会があったのを見たが、最近でも国内で年に二百人新患が出、その三分の一は九州であるという。津田さんの事を考えながら、痛ましい思いでこれを聞いた。「雪ふる音」は昭和二十九年より没年の三十八年までの八百七十首を収めている。みな熊本の菊池惠楓園における作品である。「うかららにかかはりもなき名を用い癩園に生きて来し二十年」「いたづきの秘すすべなくなりしときわが名を津田治子とは言ひそめにけり」という作もあるように、津田治子というのはいわば世を忍ぶための仮の名前だったようだ。(本名は年譜にも明らかにされていない。)そういう「特殊境涯」での作品であるから、切実無類の詠嘆が多く、読んで行って息苦しくなるような思いに駈られる。歎き、諦め、祈りというような心境が全体をやや暗く覆い、時々安らぎに似た感情も見えるが、笑いや怒りはまず見出されない。最初に挙げた四首のようなわびしいトーンが歌集にあまねく漲っているのである。昭和四十年八月号 |
|
| ← → |